2025年10月2日
「戦後80年に想う」⑪
軽薄記者の戦後80年「存在の耐えられない軽さ」(茂木和行79歳)
パート1 面白がり屋の何という「軽み」

私の記憶は、下北沢の小さな庭のおぼろげな風景から始まる。台所から直接流される下水にうごめくイトミミズの赤。ポットン・トイレのトイレ周辺に衛生上ばらまかれている石灰の白い粉。緑のつゆ草の上を飛ぶイトトンボの青。冬、雪合戦のための小さな雪小屋で、その壁にドンドンとぶつけられる雪玉の白。竹籤(ひご)をまげて作ったレールにボール紙で作った車輪と貨車をころがして遊んでいた日々。

小学6年の時、教室でボール遊びをしないとのクラスで決めた規則を、ついボールを一回弾ませたことを「茂木君が規則をやぶった!」とはやし立てられ、全員からビンタされるというお仕置きを受けたときの、ほほの痛みと情けなさ…
それからから10数年。いろいろなことがあった。…
1950年(昭和25年)朝鮮戦争
1954年(昭和29年)ビキニ環礁での水爆実験。
1960年(昭和35年)安保闘争…
こうした出来事などどこ吹く風、ボール紙で作った天体望遠鏡で宇宙の深淵を覗いている高校生の「私」がいる。底のない宇宙の暗闇に惹かれて、大学で天文学を専攻することを決意した。しかし、天文学科に進学しながら、手回し計算機で惑星の軌道を計算する日々に倦み、大学院への進学に失敗し留年、翌年、大学院の進学を諦め、毎日新聞社に入社する。
振り出しは水戸支局。県警の記者クラブでベートーベンのヴァイオリン協奏曲に耳を傾けて悦に入っていた「私」を、キャップが椅子を蹴り上げ「回ってこい!」と怒鳴る。青臭い正義論を振り回して「汚れない正義など無いぞ!」と支局長に強く言い含められる。4年目に東京本社の3方面担当、渋谷署の記者クラブで、2方面担当記者と2人麻雀。何を間違ったか、翌年、警視庁の2課4課担当に配属される。警視庁記者クラブではへたなギターでバッハなどを弾いてひんしゅくを買い、茶殻の麻雀に明け暮れる日々。大型のハイヤーで夜回りする贅沢。
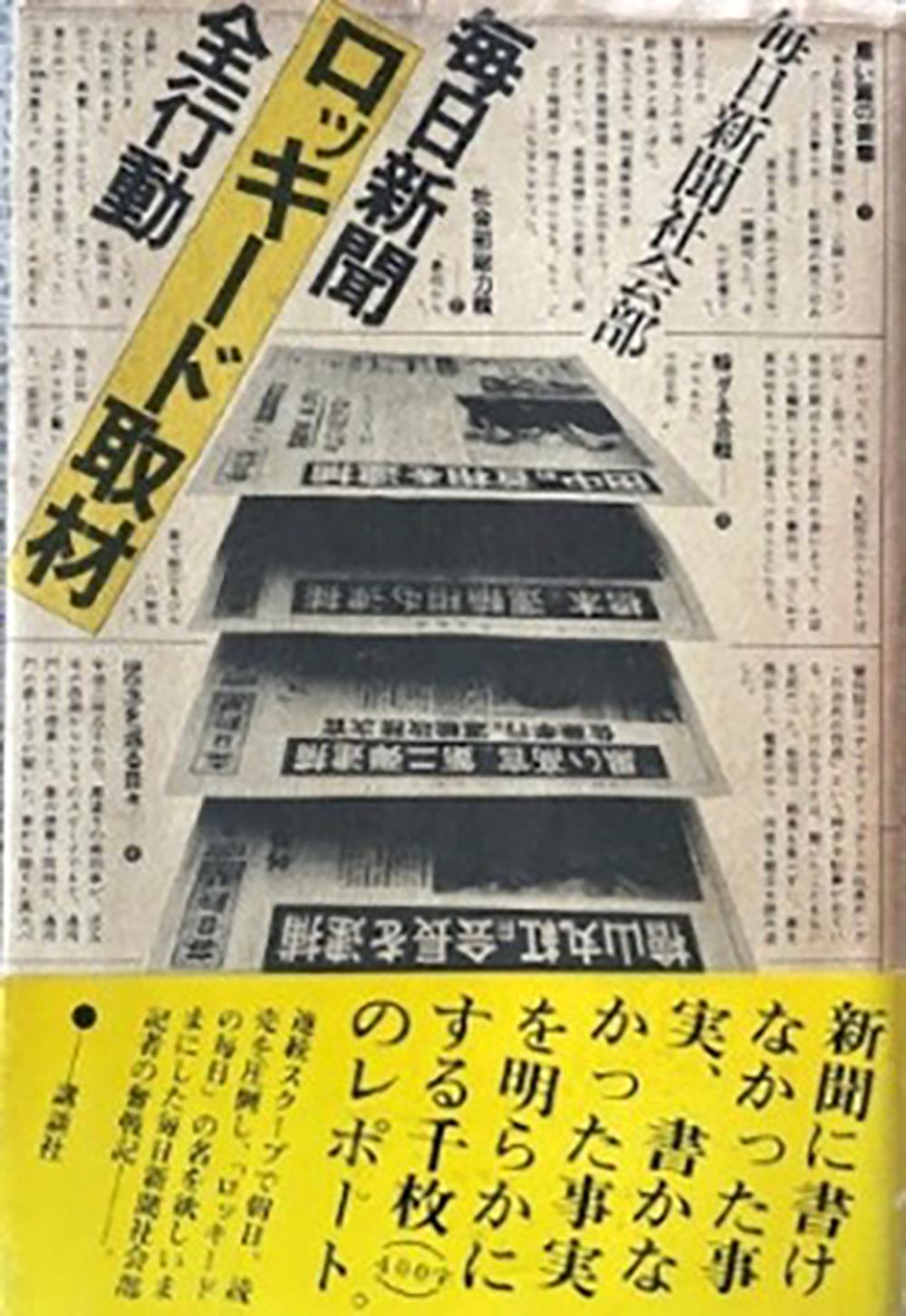

オールドメディアと揶揄され、官庁などの発表文をそのまま垂れ流す、と批判される現代の新聞。しかし、1976年(昭和51年)2月に起きたロッキード事件を総力で取材した毎日新聞の動きはそのような批判とは無縁だった。「私」は目白の田中角栄邸のゴミあさりする程度の関りだったが、ある夜回りの晩、「ほら、あれだよ、あれ。ほら、電話番号」と親しい刑事がささやく。それはお寺を装ったロッキード社の秘密基地の電話番号だった。翌朝(3月21日)、社会面のトップ記事になる。記者時代のほとんど唯一の勲章だ。
やがて、警視庁担当から八王子支局へ。軍艦に乗っていた支局長の戦争体験話「朝起きると、大部屋で寝ている者たちの全員が勃起して、林のようになっている」との話に目を丸くする。1年を経てサンデー毎日に移動。オカルトに夢中になり、スプーン曲げの超能力少年を取材。同僚たちの前で「光の玉をイメージして、足元からだんだんと頭に向かって動かし、曲がれ!曲がれ!と心の中で叫びながら、スプーンの首のところをさすってください」とやってみたら、一人が「あっ、曲がった、曲がった」との歓声に、えっ!
◇
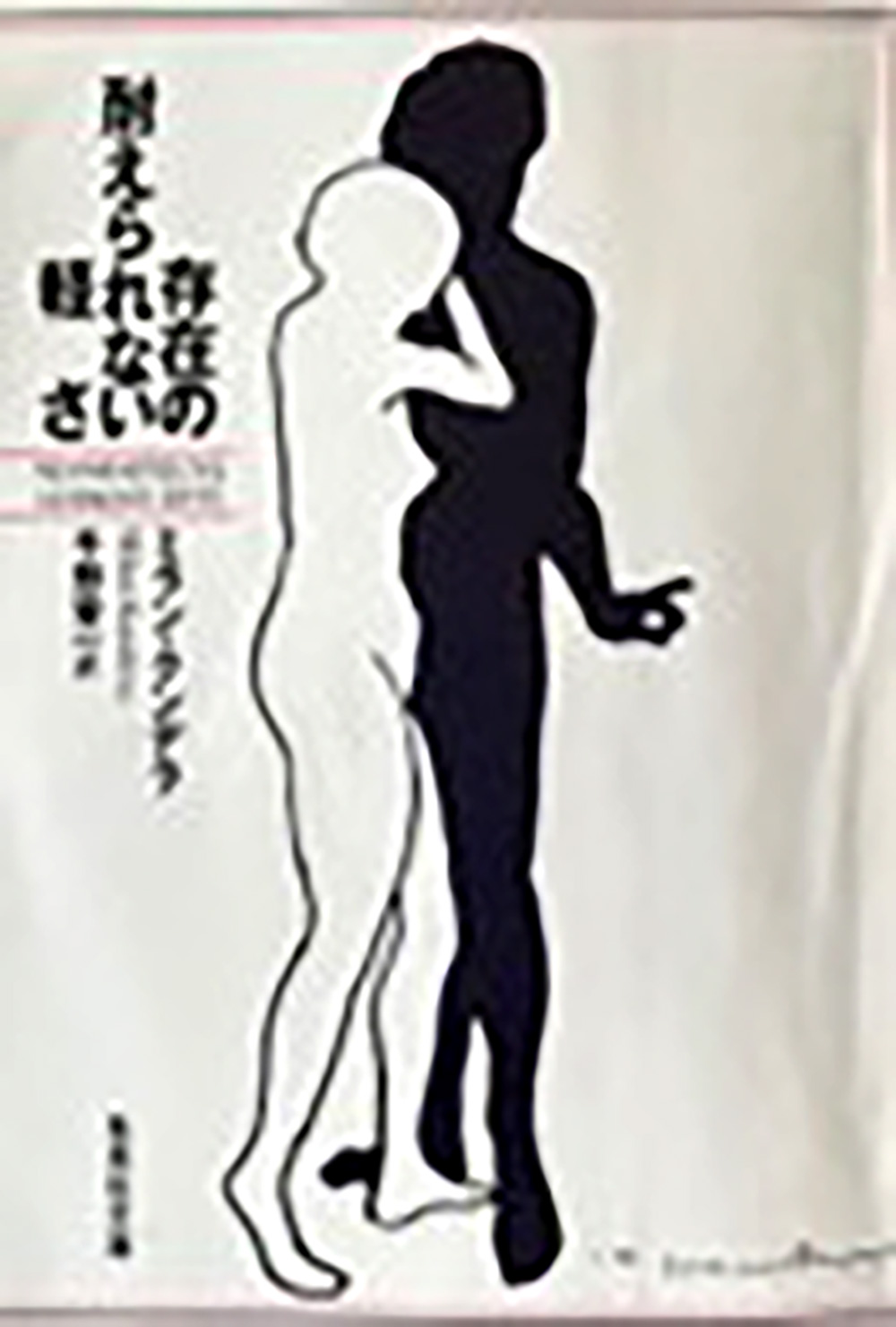
ドブチュク第一書記による「人間の顔をした社会主義」を目指した自由化・民主化の動きが、1968年8月のソ連軍の侵攻によって封じられ、「プラハの春」と称えられたチェコは再び圧政の中に沈んだ。そんな時代を背景としたミラン・クンデラの小説『存在の耐えられない軽さ』(集英社文庫、千野栄一訳)は、次のような書き出しで始まっている。
「永劫回帰という考えは秘密に包まれていて、ニーチェはその考えで、自分以外の哲学者を困惑させた。われわれがすでに一度経験したことが何もかももう一度繰り返され、そしてその繰り返しがさらに際限なく繰り返されるであろうと考えるなんて! いったいこの狂った神話は何をいおうとしているのであろうか?」
古代ギシリアの哲学者パルメニデスは、世界を、光/闇、細かさ/粗さ、暖かさ/寒さ、存在/非存在、そして軽さ/重さ、と分け、それぞれを肯定的/否定的、と分類した。ニーチェの言に従って、「永劫回帰」の人生が重い荷物を背負うようなものだ、とするならば、パルメニデスの図式によると、重い人生は肯定的、軽い人生は否定的となる。クンデラはプラハにおける医師トマーシュと田舎娘テレザの「希薄」で「軽い」アバンチュールに満ちた恋愛劇を通して、「人生が軽くてなぜいけないのか」と問いかけているように思える。
「重荷がまったく欠けていると、人間は空気より軽くなり、空中に舞い上がり、地面や、地上の存在から遠ざかり、半ば現実感を失い、その動きは自由であると同様に無意味になる」とクンデラは『存在の耐えられない軽さ』で書いている。 ひたすら面白がり、ニュースや話題を追う、まさに“地に足のついていない”浮遊するような私の「自由人生」は無意味だったのだろうか。
パート2 なぜ、私は、いま、ここに
その後、先輩に誘われて、毎日新聞を退社し、ニューズウイーク日本版の立ち上げに参加、デスクとして第二の人生が始まる。フィガロ・ジャポンの創刊で編集長。髪型から服装まで変えて、“かっこいい”姿に変身したが、女子ばかりの編集部員に対して示した「編集方針」がまったく理解されず1年で“逃げ出し”、大阪・高槻市にオープンした生命誌研究館サイエンス・ディレクターに転身。季刊「生命誌」を編集、サイエンス・オペラ「生き物が語る生き物の物語」をプロデュース。あるとき、「もう茂木さんはいらないね」との後輩部員のひそひそ話が聞こえ、新聞記者時代に取材して感激したギリシア哲学の権威に電話し、大学に移れないか相談。「つい今まで入院していた。君からの電話が初めてだよ」と言われ、この偶然を期して、松戸市の女子大へと転職、助教授を経て教授に。70歳で定年退職。
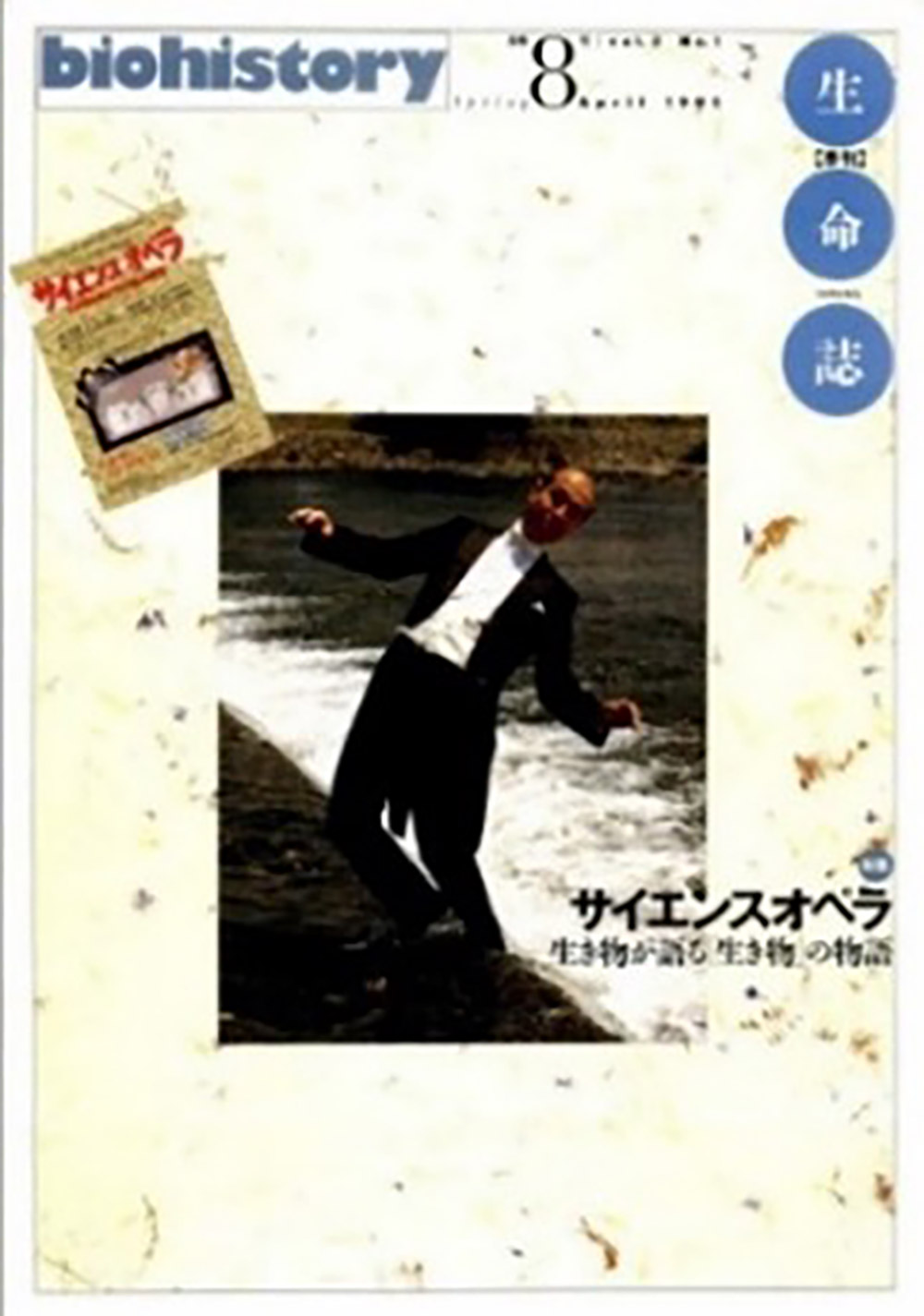
「哲学を音楽家のように奏でる」ことを目指して名刺の肩書を「哲学家」とし、シニア世代を対象とした大学での生涯学習講座「哲学サロン」を始める。記者にとって取材相手への「問いかけ」は、相手の価値観を転換し目覚めを促すソクラテスの問答法に通じる。私の「奏でる」問いかけから受講生全体に話題が広がり、講座の場に新しい発想が生まれてくる。「正義」について議論していたとき、一人の女性受講生が「アンパンマン」の歌を詠みあげてくれた。
そうだ、うれしいんだ 生きるよろこび たとえ胸の傷がいたんでも
なんのために生まれて なにをして生きるのか
こたえられないなんて そんなの いやだ
…
そうだ おそれないで みんなのために
愛と勇気だけが ともだちさ
恥ずかしながら、NHKの連続ドラマ「あんぱん」を見て、初めて漫画家やなせたかしが「アンパンマン」に込めた「愛と勇気の哲学」に触れた程度で、この正義を巡る講座のときはまったく無知だった。講座「哲学サロン」は、いまでは、「私」が逆に受講生から刺激を受ける日々が続いている。
◇
フィガロ・ジャポンを去るとき、事務の女子職員から「茂木さんって、前ばかりみているのね」と言われたことが頭から離れない。何のことはない、周りが見えない、ということに気づくまでずいぶんと時間がかかった。「周り」が見えないということは、見る対象は自分の興味だけに過ぎず、ウクライナやパレスティナに象徴される動乱する世界という「周り」など見えるわけがない。
ベートーベンの弦楽四重奏曲第16番ヘ長調の終楽章導入部に「Muß es sein?」(そうでなければならない?)、「Es muß sein!」(そうでなければならない! ) なる謎の言葉が書かれている。それは「must」なる強い決意の表明を意味し、『存在の耐えられない軽さ』のなかで、国境を監視するロシアの戦車群を横目にしながら、主人公の医師トマーシュが愛する田舎娘テレザのもとへスイスのチューリッヒから「自由のない」プラハに戻る決意の表れとして描かれている。

「軽い」私でも、このベートーベンの「Es muß sein!」(そうでなければならない! ) の力が働いたのだろうか。東日本大震災(2021年3月11日)をきっかけに噴出したエネルギー危機に、持続可能(サステナブル)なエネルギー源として「人力発電」に目を向け、足こぎ発電と足踏み発電の装置を活用する「NPO法人人力エネルギー研究所」を立ち上げた。富士河口湖町役場前広場でモーツァルトの「魔笛」の音楽を奏でながら人力で走る小型電車・魔笛号を走らせる「人力発電遊園地」を開催。その後、人力発電を組み合わせたサステナブル・オペラ「魔笛と魔法の人力発電エアロバイク」、サステナブル・オペラ:オルゴール箱の「フィガロの結婚」などをプロデュースした。
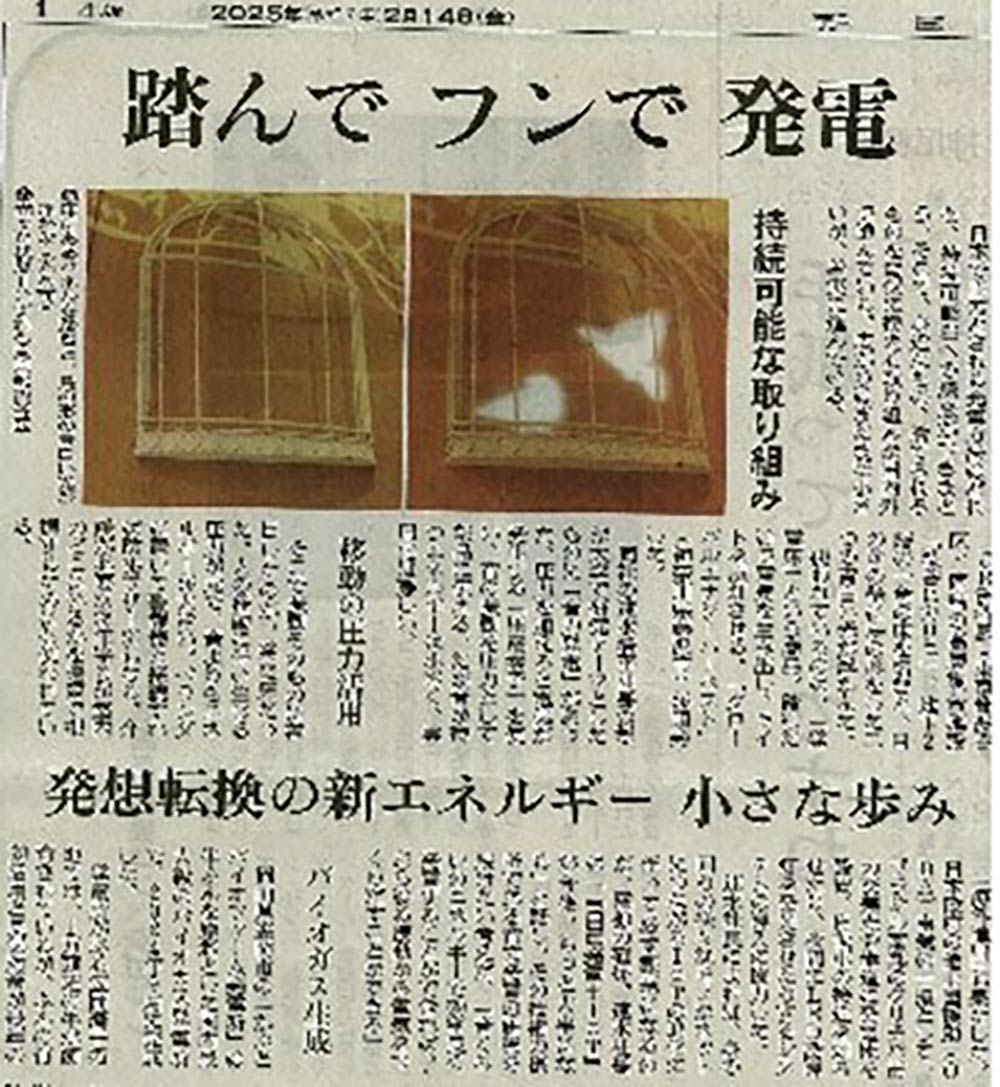
持続可能をキーワードとする「人力発電」の試みは、なかなか理解されないままだったが、最近になって「朝日新聞」が「フンで発電 持続可能な取り組み」と記事化している(2025年2月24日)のを見て、無駄ではなかった、と思い始めている。
トランプ大統領が「ガザ地区を中東のリヴィエラにする」とぶち上げたガザ・リゾート構想がある。これを逆手にとって、イスラエルが進めている222万人のガザ市民を退去させるのではなく、毎年38億ドルに上る軍事援助の一部を投資に回し、彼らの住居をつくり仕事を与え、ともにリゾートの運営に当たる。そんなアイデアをトランプ大統領に提案したい。これこそ、「Es muß sein!(そうでなければならない! )」のではないか。話題になったフェイク画像リゾート化したガザ地区にトランプ氏の黄金像……動画製作者は「風刺のつもりだった」と当惑 - BBCニュースそのままに、自身の黄金像を浜辺に立てる。トランプ君、そう決断しろよ。これこそが真の「重い」決断。しからば、君はノーベル平和賞間違いなし!
◇
「軽薄記者」が、せめて「重み」をつけようとする試みを、ニーチェは「大笑い」し、おまえの人生は「軽いまま」で「永劫回帰」するさ、と一蹴するだろうか。いや、ニーチェさんよ、そもそも「永劫回帰」などという考えは正しいだろうか。私が気になるのは、「人間は一本の考える葦である。空間によって、宇宙は私をつつむが、考えることによって、私が宇宙をつつむ」の名言で知られるフランスの哲学者パスカルの、あまり知られることのない次の言葉だ。
「なぜ私はほかのところではなく、このところに置かれているのか。私に与えられたこのわずかな時が、私よりも前にあった永遠のすべてと後すべてのほかの点ではなく、この点に割り当てられたのであろうか。いったいなぜなのか」(『パンセ』一九四)
この「私」はなぜ、昭和21年2月4日というこの時、下北沢というあの一角に、生まれたのだろうか。なぜ、ガザ地区の混乱の中に、生を受けなかったのか。アフリカの飢餓の難民の中で生まれなかったのだろうか…。
「なんのために 生まれて なにをして生きるのか…」
あのアンパンマンの歌がどこからか聞こえてくる。来世、「私」はどんな時代の、どこに、どのような形で存在するのだろうか。
◇
茂木和行さんは、1970年入社。水戸支局から社会部。サンデー毎日。TBSブリタニカへ転職。1990年5月号として創刊した「フィガロ・ジャポン」初代編集長。その後、季刊「生命誌」の編集に携わったあと、聖徳大学(松戸市)教授。NPO法人「人力エネルギー研究所」を創設。現在はオープンメデイア「私達の教育改革通信」編集者のひとり。