2025年7月7日
東大教授加藤陽子さんがベタ褒めの『公安捜査』・『内調』
5日付け毎日新聞「今週の本棚」。日本近現代史が専門の東大教授加藤陽子さんが、社会部遠藤浩二記者の『追跡 公安捜査』と元学芸部・論説委員の岸俊光さん(アジア調査会常務理事・事務局長)の『内調 内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』が取り上げている。
見出しは「監視すべき権力に向き合うスタンス」。
——『追跡』は手に汗握る調査報道であり、『内調』は研究史に残るレベルの情報機関の通史となった。二冊に共通するものは何かと問われれば、メディアの最も重要な役割は権力の監視にありと見定めた著者らのスタンスにあろう。
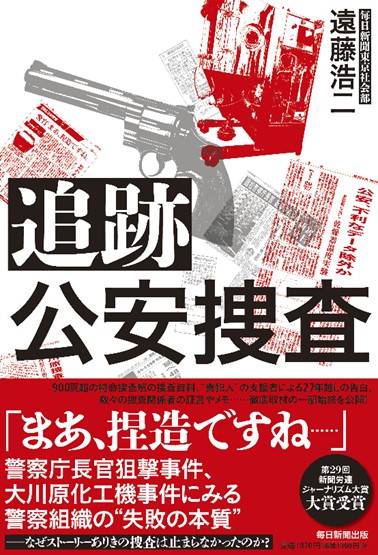
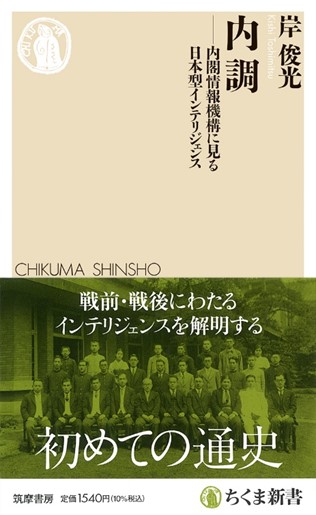
——『追跡』を書いた遠藤浩二は「持っている」記者だ。20年3月、警視庁公安部が化学機器メーカー「大川原化工機」の社長・役員ら3人を、軍事転用可能な装置を不正輸出したとする外為法違反容疑で逮捕した事件。事件を追っていた遠藤は23年12月7日、「毎日新聞」朝刊一面でスクープを放つ。起訴取消しを決めた地検と公安部との「打ち合わせメモ」を入手したうえで、複数の捜査員の証言で脇を固めた記事は、「外為法はザル法。解釈をつくれるチャンス」とばかりに公安部が見立て捜査を行い、大川原化工機を狙い撃ちにした冤罪の根幹部分に迫っていた。
——「持っている」と書いたのは、スクープだけが理由ではない。大川原化工機側は冤罪事件をうけ、東京都と国に対し国家賠償訴訟を起こし、25年5月28日、公安部の捜査と地検の起訴を違法とした東京高裁判決を得た。6月11日、東京都と国側が上告を断念し、会社側が全面勝訴した判決はここに確定した。
大団円を迎えた案件に見えたが、遠藤の筆は、公安部捜査の違法を実名で暴いただけでなく、悪性腫瘍で重態だった大川原化工機顧問への保釈請求を却下し続けた裁判官らの非理の構造にも及ぶ。『追跡』の魅力は、たまたま受かったのが毎日新聞社だった普通の若者が、鳥取支局・大阪社会部で鍛えられ、ついには「どんな相手でもいつかは喋る—」と断言するような聞き込み取材のプロとなるまでの遍歴が、瑞々しい筆致で描かれた点にもあるだろう。
——『内調』の著者・岸俊光が描いたのは、日本の情報機関の歴史だ。戦前期から、米中接近・国際通貨制度が動揺する1972年頃までをカバーした。情報機関といえば直ちに、インテリジェンス、スパイ組織といった連想が浮かぶが、日本の内閣調査室にそれはあてはまらない。対日平和条約が発効して日本が独立を回復した52年4月、吉田茂内閣によって創設された内閣総理大臣官房調査室。この後継として、57年8月、岸信介内閣が内閣官房に設置したのが、現在に続く内調に他ならない。
——研究史への本書の最大の寄与は、戦後の内調が、36年7月に広田弘毅内閣が創設した「情報委員会」以来の流れを、勤務の人的にも組織の性質上でも継承していた事実を、初代内閣情報部長・横溝光暉の資料や元内閣調査室主幹・志垣民郎の資料から明らかにしたことにある。
(堤 哲)